自然のサイクルで育てる酪農には「無駄」がない
牧場に生える野草は100種類以上ありますが、春から秋まで、牛が食べる量の草の半分を、ただ一種の「ニホンシバ」が占めています。このシバだけは最初に手植えが必要ですが、こうして山地の野草を育てる自然に沿った放牧は、理にかなっているのだと吉塚さんは言います。
「ニホンシバは、5年もあれば密生します。密生して土が見えなくなれば、1時間に100mmと大被害が出るレベルの豪雨が降っても、土は流れません。糞も流れないから肥料として活用されて、栄養たっぷりの野草が生えてくる。日本の自然はすごい力を持っていて、じつに無駄がないんです」
牧草地を利用した牧場の場合は、数年経つとお金をかけて種をまき直す必要がありますが、この山地の牧場ではそういったことが一切必要ありません。最初さえ手をかければ、そこに種が落ちて、知らないうちに牧草が増えていく。そうした自然のサイクルが、牧草と牛たちを育てているのです。

こうして読むと、山地酪農はいいことづくしのように思いますが、ひとつ難点があります。それは、野草を使って育てた牛からは「搾れる牛乳の量が少ない」ということ。飼料を与え牛舎で飼う乳牛に比べて、その量は3分の1になります。
ですが、「本来はこれが正常な搾乳量」と吉塚さん。
「いまだに農学部畜産学科は、とにかく購入飼料を食べさせて、たくさん絞ることが善だと指導しています。牛が短命でもいいから、たくさん絞って量がとれたらいいと。でもね、そこに牛の未来もないし、健康も幸せもないんです。まして人の幸せなんてないんですよ」
量を考えるなら他のエサを与えればよいのですが、田野畑の山地酪農ではそれをしません。すべては牛乳を口にする人と乳牛の健康、そして自然のため。そしてこれが、日本の当たり前の牛乳になってほしいと、この山地酪農という放牧を知ってもらうために、吉塚さんは酪農を続けているのです。
「毎回牛乳をお届けに行くと、こんな牛乳はほかにはないと、買っていただいてるのに感謝されるんです。この味だけは、なんとしても守っていきたいですね」
吉塚さんは山の開拓から始めて、約10年の歳月をかけて牧場をつくりあげ、そこから50年間、酪農をつづけています。
この山地酪農を始めたきっかけは、学生時代に恩師である猶原恭爾博士が提唱した、「山地酪農」の教えに衝撃を受けたからなのだそう。しかし、そんな猶原博士の構想はなかなか世間に受け入れられず、論文すら見てもらえずに門前払いでした。
「『そんなことは前例がないから』とみんな口を揃えて言いました。現実にそういう農家がないから、説得力がない。悔しくて仕方がなかったですね。だから私は、前例がないならつくればいいと、先生の研究を農場で実現することに決めたんです」
極貧生活が続いた〝闇地酪農〟の10年間
恩師の研究を実現させる。そう固い信念を持ち、田野畑の山林に土地を取得した吉塚さんでしたが、なんせ一からの開拓。牧場が今の形になるまでには、相当な苦労と努力がありました。
「山あり谷ありとはいいますけど、谷ばっかりでした! 経済苦がずっとありましたから」
牧場を一からつくるということは、言い換えれば牧場が完成するまでほとんど収益はないということ。
「あの頃は本当に大変で、『これは山地酪農じゃなくて、闇地酪農だ』って何回も言いましたね。とてもじゃないけど、やってられなかった。だけど、僕がそこで諦めたら……先生の研究が終わってしまう。いつもね、そう思ってこらえてきました」
吉塚さんが一番辛かったのは、電気がない時期が10年間あったこと。
それでも吉塚さんが恩師の想いを繋ぎたいという意思を崩さなかったからこそ、今の山地酪農牛乳と、乳牛たちの幸せがあるのです。


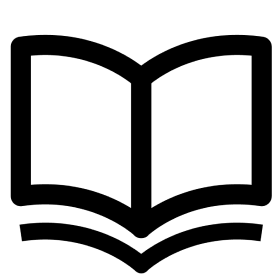 記事一覧
記事一覧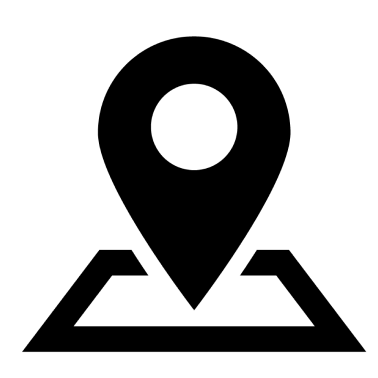 キャンプ場を探す
キャンプ場を探す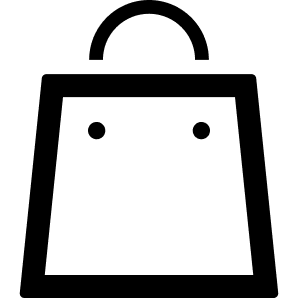 ショッピング
ショッピング
















